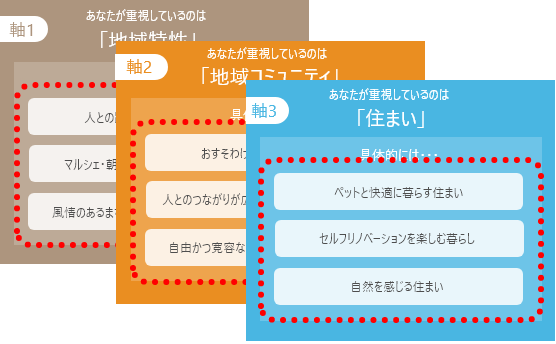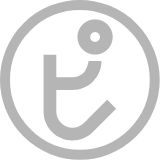-
おでんの意外なルーツ
寒い季節になると、無性に恋しくなるおでん。 身近な食材で作れるうえに、調理方法もシンプル。 レトルト食品も充実しているので、一年を通して親しまれている。 室町時代に普及した田楽豆腐から枝分かれして、江戸時代に原形が生まれた「おでん」。高度経済成長期にかけて、家庭料理に仲間入り。やがて全国各地に広がったおでんは、地域の食文化と融合し、独自の進化を遂げている。 おでんの起源とされる田楽豆腐は、串焼きにした豆腐に味噌を塗って食べる料理。 おでんとは似ても似つかぬ田楽豆腐が、どのような経緯で鍋料理へと発展したのか。辻調理師専門学校日本料理教員の大引伸昭先生はこう話す。 田楽豆腐が普及したのは室町時代とされています。 宮中に使える女房の間では、頭語に『お』を付けた『お田楽』と呼ばれており、それが転じて『おでん』になったのだとか。おでんといえば、今は煮こみスタイルをイメージしますが、その前には田楽を指す時代が、長く続いていたんですね」。

-
時代とともに「おでん」が変化
江戸時代になると田楽バリエーションも増えていき、こんにゃくやナス、魚といった具材も使われるようになる。 大引先生によると、現在のおでんのスタイルに近づくのは江戸後期からだという。 田楽から派生して、串に刺した食材をお湯で煮こむ、湯煮の田楽が登場。はじめは醤油や味噌をつけて食べていたが、のちに醤油味の煮汁を使う煮こみの調理方法が確立される。 「当時の田楽は、屋台や茶屋が提供するファストフードのようなもの。店が効率を重視したため『焼き』から『煮こみ』に派生したのかもしれませんね。結局、煮こみ田楽の方がおでんと呼ばれるようになり、田楽は別物として残り続けます」。 煮こみ田楽改めおでんは江戸っ子たちから人気を集め、明治から大正にかけて各地に伝播。関西に伝わると「関東煮(だき)」の名で発達する。これは、関西では味噌田楽がおでんとして根づいていたため。和歌山県出身の大引先生にとっては、おでんより関東煮が馴染み深い。 「うちの地元では『かんとだき』でしたね。母がよく作ってくれました。現在は関西でもおでんと呼ぶ方が主流なのではないでしょうか」。 おでんを食べるシチュエーションも時代とともに変化してきた。おでんと聞くと“一家団らんの食卓”を連想する人も少なくないだろう。しかし、大引先生は「そのイメージは昭和以降にできあがったもの」と、話す。 「江戸時代は一人一人が個別の膳で食べるのが主流でした。明治時代にちゃぶ台が登場し、大正から昭和にかけて普及すると、状況が変わります。家族で卓を囲んで食事をする機会が増えたんです。その過程でおでんのような鍋料理や大皿料理が食卓に上がるようになったと考えられます」。 田楽豆腐をルーツにもつおでんは、本家とは別物の鍋料理として発展。 地域の食文化を丸ごと受けいれる寛容さを見せ、多様に枝分かれした。ご当地おでんの広がりもまだまだ未知数。令和の時代においても、おでんの進化は止まらない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 🌟詳細はSHUN GATEで読むことが出来ます ▶SHUN GATE https://shun-gate.com/power/power_101/ ▶大引伸昭 辻調理師専門学校 日本料理教員。1986年辻調理師専門学校卒業後、同校に入職。後進の指導にあたり30年以上のキャリアを持つ。新聞社主催料理教室の講師も務める。テレビ「どっちの料理ショー」出演など、テレビや新聞など多数のメディアに協力。現在、毎日新聞「美食地質学入門」にて神戸大学の巽好幸教授と対談連載中。

ログインとユーザーネームの登録が必要です。